幼少の頃、母に連れていかれるスーパーの店先に、カップ式の自動販売機があった。
一杯70円だったと思う。コーラやメロンソーダ、ココアといったラインナップとともに、牛乳屋さんの珈琲というコーヒー飲料があった。
かわいい牛のイラストが描かれた押ボタン、コーヒー牛乳を薄めたようなすっきりした甘さ、それが私の一番のお気に入りで、日課のように飲んでいた。
ある日、何を思ったのか、ブレンドコーヒーと記されたボタンを押した。砂糖やミルク入りも選べるのだが、あえてブラックでのこだわりらしい。
ほどなくカップに注がれ、扉を開けて取り出したコーヒーと称される黒く熱い液体。
一口すすり、なるほどこれが大人の味か、などと思うわけがなく、苦くて不味くてとても飲めたものではない。このチャレンジは無謀だったと即座に理解した。
ただ買ってしまった以上は(棄てたら母に怒られると思ったのだろう)ちびちびと口に含むのだが、その度に酷い顔をしていたようで、知らない大人2人に「あの子コーヒー飲んでる!」とケタケタ笑われた。一向に減らないコーヒーは秘密裏に溝に流して棄てた。
それが私のコーヒー初体験である。
それから田舎を出るまで、コーヒーとはインスタントコーヒーをお湯で溶かして、砂糖と牛乳を入れる甘い飲み物だった。
高校を出ると就学の為に上京した私は、阿佐ヶ谷を拠に、60〜70年代の音楽、文学、漫画に嵌り、それと同時に、カウンターカルチャーと喫茶店の文化を知るようになる。
高円寺の七つ森と国分寺のほんやら洞がお気に入りで、そこに居る客の知的な雰囲気も好きだった。
名曲喫茶のライオン、ジャズ喫茶のマサコでは、シラフで酩酊するような不思議な感覚を覚えた。
音楽とタバコの煙にまみれて飲む、深煎りのコーヒー。当時の私にとってコーヒーは麻薬のようなものだったのだと思う。
すっかりコーヒーが欠かせない体となった私は、カリタの手挽きミルと、コーノのドリッパーを入手し、自宅でも淹れ方に凝り始める。
だが、コーヒー豆を売っている専門店は好きではなかった。好みを探られても回答を持たないし、粉にお挽きしますかと尋ねられるのも嫌だった。求めていたのはグルメではなかったからだと思う。
とりあえず豆はスーパーなどで買うのだが、段々と物足りなくなってくる。
そんな折、コーヒー豆を自宅で焙煎できることを知った。早速生豆を調達し、ぎんなん煎りで焙煎をするようになった。
今思えばいい加減な焙煎だったが、どの豆もそれなりに美味く、なかなかのウデだと自画自賛してしまうのだった。
なんとなく飲んでいたコーヒーが主体性を持ち、良し悪しを明確に意識するようになったのは焙煎がきっかけだと思う。
30歳を過ぎたある時、生豆業者のホームページで富士珈機製の中古焙煎機が売られているのを見つけた。
すぐに電話をするが既に売り切れだという。しかし、以前売れた同型が返品になったから、それでよければ用意できるらしい。
現物も見ずに即決で買った。2001年製、半熱風式の1キロ焙煎機だった。
賃貸の狭いキッチンを占拠した業務用焙煎機。この環境で焙煎すればクレームになり追い出されるのは必至だろう。
防音の為に吸音材を敷き詰めた巨大な木箱を自作し、ニオイ対策に活性炭を詰めたフィルターを作った。
DIYは功を奏し、周りに迷惑をかけること無く趣味に勤しむことができた。
コーヒー豆を焼いて売るという明快な商いに憧れを抱くようになったのもこの頃である。
そして、いわゆる氷河期世代らしい紆余曲折も経験した私は、いつしか屋根裏のような狭いテナントでコーヒー豆屋をやっている。
こだわりなどと当たり前の事を歯が浮くような言葉で語るのは避けたいが、みっともないコーヒーではみっともないので、立派なコーヒーを売りたいと、日々悩んでいるらしい。

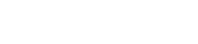
返信を残す